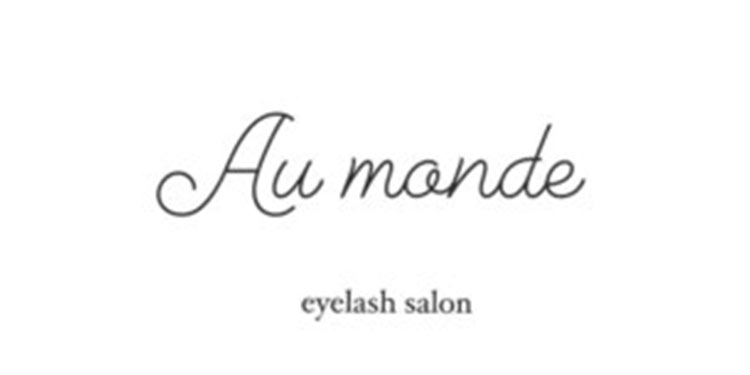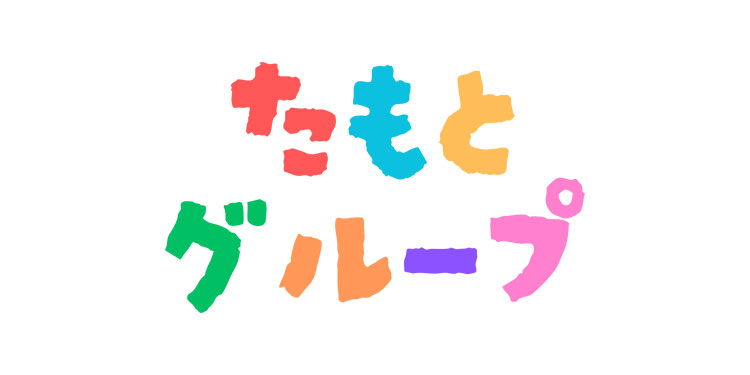肺とは
肺(はい)は、胸の中にある臓器で、空気中の酸素を取り入れ、二酸化炭素を体外に排出する働きを持っています。左右に1つずつあり、右肺は3つ、左肺は2つの葉(よう)に分かれています。肺の内部は細かい気管支と肺胞からできており、血液との間でガス交換を行っています。
肺がんとは
肺がんは、肺の気管支や肺胞を構成する細胞ががん化して増える病気です。日本では年間約13万人が新たに診断され、がんによる死亡原因の第1位を占めています。
肺がんは大きく「非小細胞肺がん(約85%)」と「小細胞肺がん(約15%)」に分かれます。非小細胞肺がんは進行が比較的ゆるやかですが、小細胞肺がんは急速に広がる傾向があります。
主な原因・リスク

最も大きな原因は喫煙です。タバコの煙に含まれる多くの発がん物質が肺の粘膜を傷つけ、がんを引き起こします。受動喫煙もリスクとなります。
その他の要因として、大気汚染、アスベスト(石綿)、ラドンガスへの曝露、遺伝的要因なども知られています。最近では、喫煙歴がない方でも発症する「EGFR遺伝子変異」や「ALK融合遺伝子」などの分子異常による肺がんも注目されています。
主な症状
早期の肺がんはほとんど症状がありません。進行すると、咳が続く、血痰が出る、息切れ、胸の痛み、声のかすれ、発熱、体重減少などが現れます。
がんが進行してリンパ節や骨、脳に転移すると、肩や背中の痛み、頭痛、むくみなどの症状が出ることもあります。風邪が長引くような症状が続く場合は、早めの検査が大切です。
診断方法
胸部X線検査やCT検査で異常が見つかった場合、精密検査として気管支鏡検査で病変部から細胞や組織を採取し、病理診断を行います。
また、PET-CTやMRIなどで転移の有無を確認します。確定診断後には、遺伝子変異(EGFR、ALK、ROS1、KRASなど)の検査を行い、薬物療法の選択に役立てます。
治療判断に使われる分類と治療方針
肺がんの治療を決める際には、TNM分類を使います。
Tは腫瘍の大きさや肺内での広がり、Nはリンパ節転移の有無、Mは遠隔転移の有無を表します。この組み合わせでステージI〜IVに分けられます。
また、「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」では治療方針が大きく異なります。
非小細胞肺がん(NSCLC)
ステージIは、がんが肺の中に限局しており、リンパ節転移がない段階です。この場合は手術(肺葉切除+リンパ節郭清)が基本治療です。手術が難しい場合は体幹部定位放射線治療(SBRT)で治癒を目指します。
ステージIIは、がんがやや大きいか、近くのリンパ節に転移がある段階です。手術が可能であれば外科切除が行われ、術後に再発を防ぐための補助化学療法を行うことがあります。
ステージIIIは、がんが周囲の臓器やリンパ節(縦隔など)に広がっている段階です。この場合は、手術・放射線治療・化学療法を組み合わせた集学的治療が行われます。切除困難な場合は化学放射線療法(CCRT)を行い、その後に免疫療法(デュルバルマブ)を追加することもあります。
ステージIVは、がんが反対側の肺や遠隔臓器(骨・脳・肝臓など)に転移している段階です。この場合は手術ではなく薬物療法が中心です。分子標的薬(EGFR阻害薬・ALK阻害薬など)や免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ・ペムブロリズマブなど)が用いられ、がんの進行を抑えます。
小細胞肺がん(SCLC)
小細胞肺がんは進行が早いため、限局型(片肺にとどまる)と進展型(全身に広がる)に分けて治療します。
限局型では化学放射線療法(CCRT)が中心で、進展型では抗がん剤治療(プラチナ系+エトポシド)に加えて免疫療法(アテゾリズマブなど)が用いられます。
予防・早期発見

禁煙が最も重要な予防策です。受動喫煙を避けることも大切です。
また、職業的なアスベスト曝露の回避、大気汚染対策も有効です。
早期発見のためには、定期的な胸部CT検査が有用で、特に喫煙歴のある方は毎年の検査をおすすめします。
参考文献
- 日本肺癌学会『肺癌診療ガイドライン 2023年版』
- 国立がん研究センター がん情報サービス: https://ganjoho.jp
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Lung Cancer, Version 2024
- American Cancer Society: Lung Cancer Guide 2023