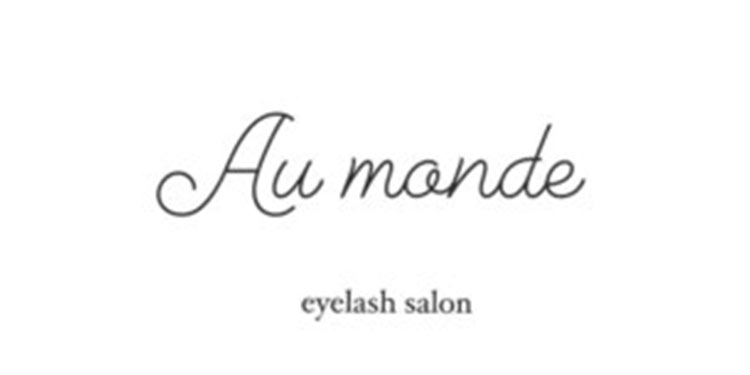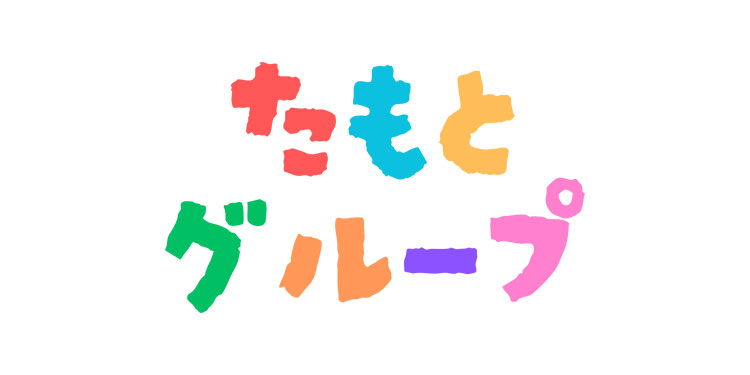大腸とは
大腸(だいちょう)は、小腸の後に続く約1.5mの長い管状の臓器で、「盲腸」「結腸」「直腸」「肛門」から構成されています。主な役割は、食べ物の残りから水分を吸収し、便を形成して体外に排出することです。大腸の内側は粘膜で覆われており、ここに炎症やポリープができると、長い年月をかけてがんに進行することがあります。
大腸がんとは
大腸がんは、大腸の粘膜にある細胞ががん化して発生する病気です。日本では年間約15万人が新たに診断され、がんによる死亡数では上位を占めています。
右側(上行結腸や横行結腸)と左側(下行結腸やS状結腸、直腸)で症状や性質がやや異なります。右側は進行しても症状が出にくく、左側は便通異常や出血などが早めに出る傾向があります。
主な原因・リスク
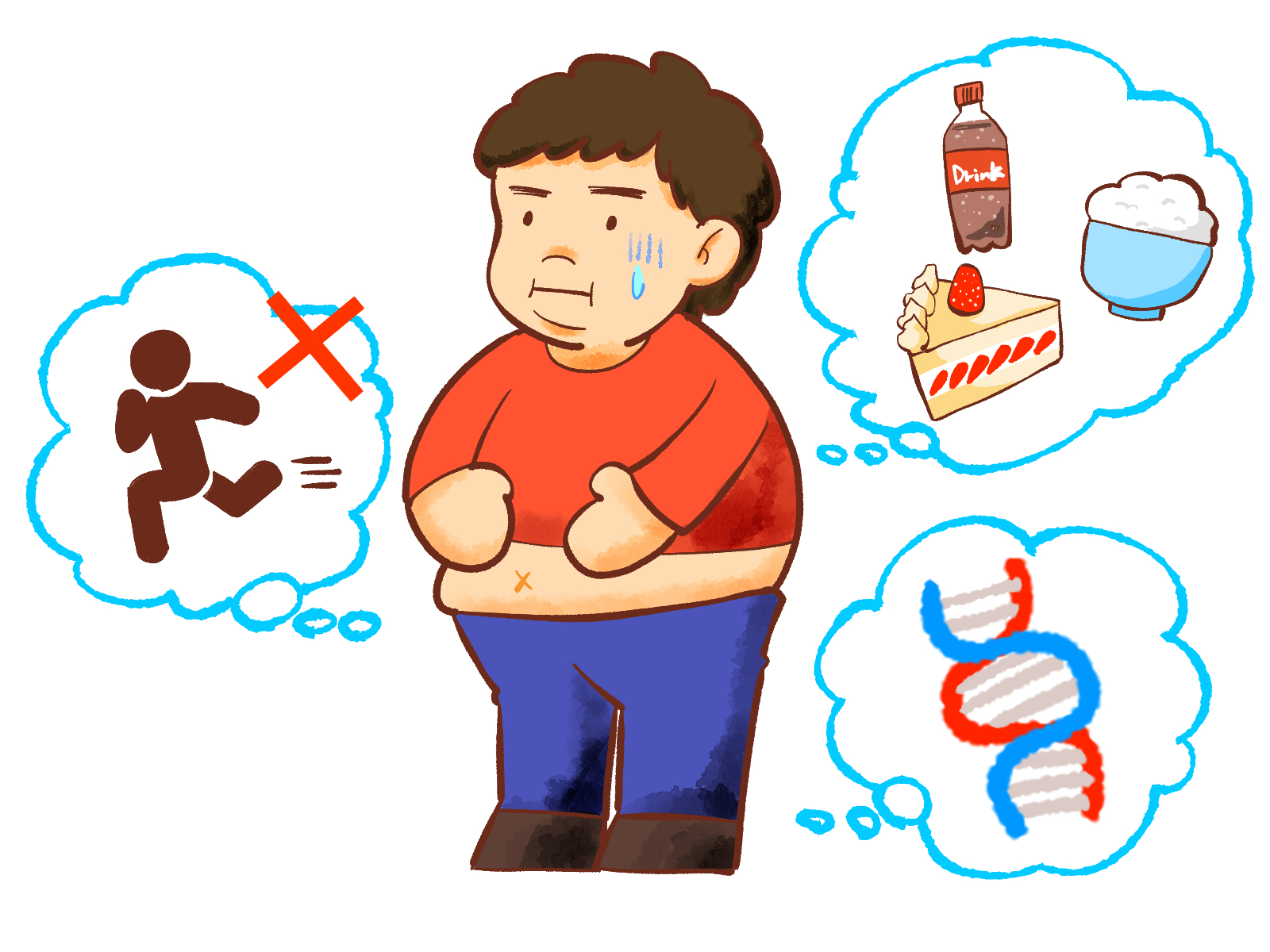
大腸がんの発症には、生活習慣と遺伝的要因の両方が関係します。
赤肉や加工肉の多い食事、食物繊維の不足、肥満、運動不足、喫煙、過度の飲酒などはリスクを高めます。
また、家族に大腸がんのある方や、遺伝性大腸がん(リンチ症候群、家族性大腸腺腫症など)を持つ方は特に注意が必要です。慢性の炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)もリスク因子です。
主な症状
早期の大腸がんはほとんど症状がありません。進行すると、便に血が混じる、下痢や便秘を繰り返す、便が細くなる、腹部の張り、貧血、体重減少などが現れます。
右側のがんでは貧血や倦怠感、左側では出血や排便の異常が多く見られます。こうした症状が続く場合は早めの検査が重要です。
診断方法
大腸内視鏡検査が最も重要です。ポリープや腫瘍を直接観察し、必要に応じて組織を採取して病理検査を行います。
さらにCTやMRI検査で、がんの進行度や転移の有無を確認します。
血液検査では、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)を測定し、治療後の経過観察にも使われます。
治療判断に使われる分類と治療方針
大腸がんの治療を決める際には、TNM分類を使います。
Tは腫瘍が大腸の壁のどこまで深く入り込んでいるか、Nはリンパ節転移の有無、Mは遠隔転移の有無を表します。この組み合わせでステージI〜IVに分けられます。
ステージIは、がんが粘膜または粘膜下層にとどまっている早期がんです。この段階では、内視鏡的切除(EMR・ESD)や局所切除手術で根治できる場合があります。
ステージIIは、がんが筋層を超えて広がっているが、リンパ節転移がない段階です。この場合は手術(腹腔鏡または開腹による結腸切除+リンパ節郭清)が基本です。再発リスクが高い場合には、術後に補助化学療法を行います。
ステージIIIは、リンパ節に転移がある段階です。手術に加え、抗がん剤治療(FOLFOX、CAPOXなど)を行うのが一般的です。がんの位置によっては、術前化学療法や放射線治療を組み合わせて再発を防ぐこともあります。
ステージIVは、がんが遠くの臓器(肝臓・肺など)に転移している段階です。根治は難しい場合が多く、全身化学療法や分子標的薬(ベバシズマブ、セツキシマブなど)による治療が中心となります。
一部の患者さんでは、転移巣を切除することで長期生存が期待できるケースもあります。
予防・早期発見

バランスの取れた食生活(食物繊維を多く、加工肉を控える)、禁煙・節酒、適度な運動が予防につながります。
また、40歳以上では年に1回の便潜血検査が推奨され、陽性であれば大腸内視鏡検査を受けることが重要です。
ポリープのうちに切除することで、大腸がんの予防が可能です。
参考文献
- 日本大腸癌研究会『大腸癌治療ガイドライン 2023年版』
- 国立がん研究センター がん情報サービス: https://ganjoho.jp
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Colon and Rectal Cancer, Version 2024
- American Cancer Society: Colorectal Cancer Guide 2023