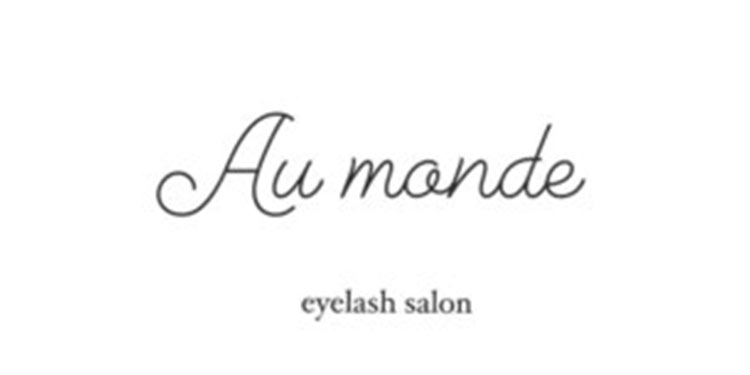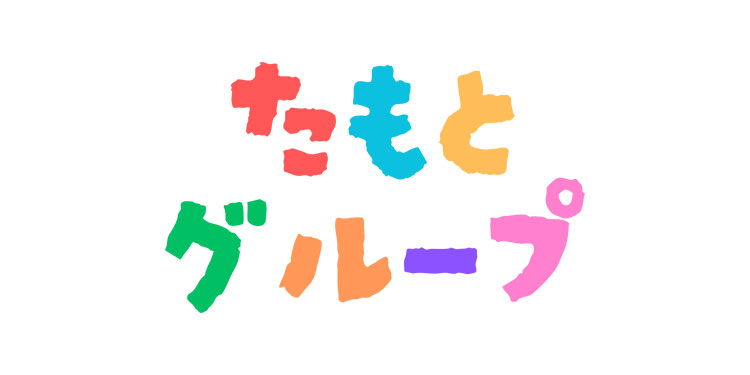骨とは
骨は、体を支えるだけでなく、カルシウムなどのミネラルを貯蔵し、骨髄で血液をつくる重要な臓器でもあります。常に古い骨を壊し(骨吸収)、新しい骨をつくる(骨形成)という代謝が行われています。
骨肉腫とは
骨肉腫(こつにくしゅ)は、骨をつくる「骨芽細胞」ががん化して異常に増殖する悪性腫瘍です。骨原発の悪性腫瘍の中で最も多く、特に10〜20歳代の成長期の若年層に多く発生します。
発生部位は膝(大腿骨遠位部・脛骨近位部)や上腕骨に多く見られますが、全身のどの骨にも起こる可能性があります。
主な原因・リスク
多くの場合、明確な原因は不明です。まれに放射線治療後やPaget病などの骨疾患に続発することがあります。
また、Li-Fraumeni症候群などの遺伝的素因が関与することもあります。
主な症状

初期には運動時の違和感や軽い痛みが出る程度ですが、進行すると次のような症状が現れます。
- 持続する痛み(安静時や夜間も続く)
- 腫れやしこり
- 関節の動かしにくさ
- 骨折しやすくなる(病的骨折)
痛みが長く続く場合には、整形外科での画像検査が重要です。
診断方法
X線・MRI・CTなどで腫瘍の位置や骨への浸潤の程度を確認します。肺転移が多いため、胸部CTも行います。
確定診断には生検(針生検または切開生検)を行い、病理検査で骨形成を伴う悪性細胞を確認します。
腫瘍マーカーとしてALP(アルカリフォスファターゼ)やLDHが高値になることがあります。
治療判断に使われる分類と治療方針
骨肉腫の治療を決める際には、TNM分類を使います。Tは腫瘍の大きさと骨内・骨外への広がり、Nはリンパ節転移の有無、Mは遠隔転移の有無を表します。この組み合わせでステージI〜IVに分けられます。
ステージIは、悪性度が低く、骨内にとどまっている段階です。手術による広範囲切除が基本です。可能な限り手足を温存し、人工関節や骨移植による再建が行われます。
ステージIIは、高悪性度で骨内にとどまっている段階です。術前化学療法(ネオアジュバント療法)を行い、腫瘍を小さくしてから手術を行います。代表的な薬剤はメトトレキサート、シスプラチン、ドキソルビシンなどです。
ステージIIIは、局所進行または骨外に広がっている段階です。化学療法+手術+放射線療法の併用が検討されます。切除が困難な場合は、患肢切断が選択されることもあります。
ステージIVは、肺などへの遠隔転移がある段階です。根治は難しいですが、全身化学療法により延命や症状緩和を目指します。転移巣が限られている場合は外科的切除を行うこともあります。
予防・早期発見
骨肉腫を予防する方法は確立されていませんが、「長引く骨の痛み」や「成長期に片側だけに起こる腫れ」は注意が必要です。
整形外科でのX線やMRI検査で早期に発見できれば、手足を温存しながら治療できる可能性が高まります。
参考文献
- 日本整形外科学会『骨・軟部腫瘍診療ガイドライン 2023年版』
- 国立がん研究センター がん情報サービス: https://ganjoho.jp
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Bone Cancer, Version 2024
- American Cancer Society: Osteosarcoma Facts & Figures 2023